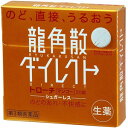オラドールSトローチ販売中止の真相!なぜ消えた?理由とメーカー情報、買える場所と代替品まで徹底解説

「あれ?いつも買ってたオラドールSトローチ、最近見かけないな…」
のどの痛みや不快感にスッと効いてくれて、愛用していた方も多い「オラドールSトローチ」。
いざ必要になって薬局やドラッグストアに行っても、棚から消えていて戸惑った経験はありませんか?
この記事では、なぜオラドールSトローチが販売中止になってしまったのか、その詳しい理由からメーカー情報、そして気になる代替品まで、あなたの疑問に答えます!
(この記事は「どこストア」が執筆しています)
・突然店頭から消えた?販売終了が確認された時期
・気になる製造メーカーはどこ?会社情報とこれまでの歩み
・オラドールSトローチの有効成分と具体的な内容物を再確認
・かつての販売場所(薬局・ドラッグストア・オンラインショップ)を振り返る
- オラドールSトローチが「販売中止」になった本当の理由とは?
- 突然店頭から消えた?販売終了が確認された時期
- 気になる製造メーカーはどこ?会社情報とこれまでの歩み
- オラドールSトローチの有効成分と具体的な内容物を再確認
- かつての販売場所(薬局・ドラッグストア・オンラインショップ)を振り返る
- オラドールS愛用者が続出!高い評価を得ていた魅力と特長
- 「もう買えないの?」販売中止の決定打となった背景事情を深掘り
- 類似品で代用できる?成分が近い代替トローチ徹底比較
- 販売再開の可能性はある?メーカーへの問い合わせ状況と最新情報
- 【必見】今後ののどケアに!成分・効果で選ぶおすすめトローチ3選
- オラドールSトローチ販売中止に関するSNSやユーザーの反応
- なぜトローチの販売中止は起こるのか?医薬品の裏事情
- まとめ:オラドールSトローチの販売中止理由と今後の対策
オラドールSトローチが「販売中止」になった本当の理由とは?

多くの方に愛用されていた「オラドールSトローチ」ですが、2024年現在、残念ながら販売中止(正確には「販売終了」または「製造終了」)となっています。
「あんなに良い薬だったのに、どうして?」と疑問に思いますよね。
私も愛用者の一人だったので、そのショックはよく分かります。
この販売中止の背景には、いくつかの理由が考えられます。
メーカーから明確に「これが理由です!」と大々的に公表されているわけではありませんが、医薬品業界の動向や一般的な流れから推測できる主な理由を深掘りしてみました。
理由その1:採算性の問題(利益が出にくくなった)
まず考えられるのが、「採算性の問題」です。
医薬品を製造・販売し続けるには、当然ですがコストがかかります。
原材料費、製造ラインの維持費、品質管理費、物流費、そして広告宣伝費…。
これらのコストに対して、売上が見合わなくなってくると、企業としてはその製品の製造を続けるのが難しくなります。
特にトローチのような一般用医薬品(OTC医薬品)は、競争が非常に激しい分野です。
次から次へと新しい製品が登場し、価格競争も起こりやすい。
オラドールSトローチは非常に優れた製品でしたが、もしかすると近年の原材料高騰のあおりを受けたり、他の競合製品との競争の中で、メーカーが期待するほどの利益を上げ続けることが難しくなったのかもしれません。
古い薬、長く愛されている薬ほど、薬価(薬の公定価格)が下がっていく傾向もあり、作り続けるほど赤字になる、なんていうケースも残念ながら存在します。
オラドールSトローチがそこまで極端だったかは分かりませんが、利益が出にくい構造になっていた可能性は否定できません。
理由その2:成分や製造ラインの維持が難しくなった
次に考えられるのは、「製造上の問題」です。
オラドールSトローチに含まれる特定の有効成分や、添加物(味や形を整える成分)の調達が難しくなった、という可能性です。
特に、世界的な情勢の変化などで、特定の原材料が手に入りにくくなったり、価格が異常に高騰することは珍しくありません。
また、医薬品の製造ラインは非常に精密で、厳しい品質管理(GMPという基準があります)が求められます。
オラドールSトローチを製造していた機械や設備が老朽化し、その更新に莫大な費用がかかる場合。
「それなら、いっそ新しい別の製品に注力しよう」という経営判断が下されることもあります。
安定した品質で製品を供給し続けることが、メーカーの事情によって困難になった、というパターンですね。
理由その3:製品ラインナップの見直し(選択と集中)
企業が成長していく過程で必ず行われるのが、「製品ラインナップの見直し」です。
これは「選択と集中」とも呼ばれます。
企業が持つリソース(人、モノ、カネ)は限られていますから、すべての製品に同じだけ力を注ぐことはできません。
より将来性のある分野や、もっと利益が見込める新製品にリソースを集中させるために、既存の製品(たとえそれが良い製品であっても)の販売を終了する、という経営戦略です。
オラドールSトローチの製造販売元は、他にも多くの医薬品や製品を扱っていると考えられます。
その中で、「オラドールSトローチ」が整理の対象となってしまった…。
長年の愛用者からすると非常に寂しいことですが、企業経営の観点からは、こうした判断は日常的に行われているのです。
結局のところ、これら複数の要因が複雑に絡み合って、「販売中止」という決定に至ったのだと推測されます。
決して製品の品質に問題があったとか、副作用が多発したとか、そういったネガティブな理由ではない(もしそうなら、もっと大々的に情報が公開されるはずです)ということは、覚えておいてくださいね。
突然店頭から消えた?販売終了が確認された時期

「そういえば、いつから見かけなくなったんだろう?」と、販売終了の時期が気になる方も多いでしょう。
明確な「〇月〇日をもって販売終了」という全国一斉のアナウンスは、あまり大々的には行われなかった印象です。
医薬品の販売終了は、多くの場合、次のような流れをたどります。
- メーカーが製造を終了(生産完了)。
- メーカーから卸売業者への出荷が停止される。
- 卸売業者の在庫がなくなり次第、薬局やドラッグストアへの納品が終了する。
- 各店舗の店頭在庫がなくなり次第、販売終了となる。
このため、地域や店舗によって、店頭から姿を消した時期にはバラつきがあります。
SNSや個人のブログなどを調べてみると、だいたい2022年頃から「見かけなくなった」「メーカー製造終了らしい」といった声が上がり始め、2023年には「ほぼ手に入らなくなった」という状況が定着したようです。
2025年現在では、通常の薬局やドラッグストアの店頭で見つけることは、ほぼ不可能と言っていいでしょう。
メーカーが生産を終了しても、しばらくは市場に在庫(流通在庫)が残っています。
そのため、「A店ではもう売り切れてたけど、B店にはまだ残ってた!」というタイムラグが発生するんですね。
私も、2023年の初め頃に「もしかして製造終了した?」と焦って近所のドラッグストアを数軒ハシゴしましたが、すでにもうどこにも置いてありませんでした…。
もっと早く気づいていれば、少し買い置きできたのに…と悔やんだのを覚えています。
もし、今でも奇跡的に店頭在庫を見つけたとしても、医薬品には「使用期限」があります。
製造終了から時間が経っているため、使用期限が切れているか、残りわずかである可能性が非常に高いです。
期限切れの薬は効果がなかったり、体に悪影響を及ぼす可能性もあるため、購入・使用は絶対に避けてくださいね。
気になる製造メーカーはどこ?会社情報とこれまでの歩み

オラドールSトローチを製造・販売していたのは、どの会社だったのでしょうか。
長年お世話になっていた製品なのに、意外とメーカー名まで意識していなかった、という方も多いかもしれません。
オラドールSトローチは、いくつかの会社が関わっていましたが、最終的に販売元となっていたのは、「第一三共ヘルスケア株式会社」です。
第一三共ヘルスケア株式会社とは?
第一三共ヘルスケアと聞けば、「あ、あの会社か!」とピンとくる方も多いはず。
「ロキソニンS」や「ルル」、「マキロン」など、誰もが知っている有名なお薬をたくさん世に送り出している、日本の大手製薬会社グループの一員です。
- 会社名: 第一三共ヘルスケア株式会社
- 設立: 2005年(ただし、母体となる三共・第一製薬は非常に長い歴史を持っています)
- 主な製品: ロキソニンS(解熱鎮痛薬)、ルル(総合かぜ薬)、ガスター10(胃腸薬)、トランシーノ(シミ改善薬)など
- 特徴: 医療用医薬品(お医者さんが処方する薬)で培った技術や成分を、一般用医薬品(ドラッグストアで買える薬)に応用するのが得意な会社です。
オラドールSトローチも、元々は医療用で使われていた成分をトローチにした製品でした。
まさに第一三共ヘルスケアの得意分野だったわけですね。
オラドールSトローチの歴史(販売元の変遷)
実は「オラドール」というブランドは、かなり長い歴史を持っています。
もともと、オラドールSトローチのルーツをたどると、「藤沢薬品工業」(現在の「アステラス製薬」の一部)という会社が関わっていました。
その後、販売元が「ゼファーマ」という会社に移り、さらにそのゼファーマが第一三共ヘルスケアに吸収合併される、という変遷をたどっています。
ちょっと複雑ですが、流れは以下の通りです。
- 藤沢薬品工業などが開発・販売。
- ゼファーマ(山之内製薬と藤沢薬品工業の一般用医薬品部門が統合)が販売。
- ゼファーマが第一三共ヘルスケアに吸収合併される(2007年頃)。
- 第一三共ヘルスケアが「オラドールSトローチ」として販売を継続。
- そして、2022年~2023年頃に販売終了。
このように、長い歴史の中で多くの会社に引き継がれながら、私たち消費者のもとに届けられていた薬だったのです。
これだけ長く愛されてきた製品がなくなってしまったのは、やはり「選択と集中」という経営戦略の影響が大きかったのではないか…と、改めて感じさせられますね。
オラドールSトローチの有効成分と具体的な内容物を再確認

「オラドールSトローチが、他のトローチと何が違ったのか?」
「なぜあんなによく効いたと感じたのか?」
その秘密は、やはり「有効成分」にあります。
ここで一度、オラドールSトローチの内容物について、詳しくおさらいしてみましょう。
オラドールSトローチ(多く流通していたのは20錠入りの箱でした)の主な有効成分は、以下の通りです(1錠中)。
| 有効成分名 | 含有量 | 主な働き |
|---|---|---|
| 塩化デカリニウム | 0.25mg | 殺菌・消毒作用 |
| キキョウエキス | 20mg (原生薬換算量 80mg) |
去痰(たん切り)・排膿(うみ出し)作用 |
| カンゾウ抽出末 | 17.5mg (原生薬換算量 250mg) |
抗炎症(はれを鎮める)作用 |
最大の特長「塩化デカリニウム」
オラドールSトローチの最大の特長であり、人気の理由だったのが、「塩化デカリニウム」という殺菌成分です。
多くのトローチやのど飴に含まれている殺菌成分は、「セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)」という成分です。
もちろんCPCも優れた殺菌成分なのですが、一部の方にとっては「味がちょっと苦手」「独特の苦みがある」と感じることもありました。
それに対して「塩化デカリニウム」は、比較的風味が良く、殺菌作用も持続しやすいという特長がありました。
この「塩化デカリニウム」を配合している一般用医薬品のトローチは、実はオラドールSトローチがほぼ唯一無二の存在だったのです。
「オラドールじゃないとダメなんだ!」という愛用者が多かったのは、この「塩化デカリニウム」の効き目や風味が、ご自身の体質や好みにピッタリ合っていたからなんですね。
生薬成分による「はれ」と「たん」へのアプローチ
さらに、オラドールSトローチは殺菌成分だけでなく、「キキョウ」と「カンゾウ」という2種類の生薬成分も配合していました。
- キキョウエキス: のどに絡んだたんを排出しやすくする「去痰作用」があります。のどがイガイガ・ゴロゴロするときに助かります。
- カンゾウ抽出末: のどの炎症や「はれ」を鎮める「抗炎症作用」があります。のどが赤く腫れて痛いときに頼りになる成分です。
つまり、オラドールSトローチは、
- 塩化デカリニウムで、のどのバイ菌を「殺菌・消毒」し、
- カンゾウで、すでに起きてしまった「炎症・はれ」を鎮め、
- キキョウで、不快な「たん」を出しやすくする。
という、のどのトラブルに対して多角的にアプローチできる、非常にバランスの取れた処方だったのです。
添加物について
このほか、トローチとしての形を保ったり、味を調えたりするために、添加物として白糖、ゼラチン、ステアリン酸Mg、香料などが含まれていました。
あの独特の、少し甘くてスーッとする風味は、これらの成分によって作られていたんですね。
(ちなみに、シュガーレスタイプも存在していました)
かつての販売場所(薬局・ドラッグストア・オンラインショップ)を振り返る

オラドールSトローチは、一般用医薬品(OTC医薬品)の中でも「指定医薬部外品」に分類されていました。
(※時期やパッケージによっては「医薬品」分類だった可能性もありますが、多くは「指定医薬部外品」として扱われていました)
そのため、薬剤師さんがいなくても登録販売者さんがいるお店であれば、比較的どこでも購入することができました。
実店舗での販売場所
まさに「町の薬箱」のような存在でしたね。
以下のようなお店の、のど飴やトローチが並んでいるコーナーの定番商品でした。
- 全国のドラッグストア(マツモトキヨシ、ウエルシア、スギ薬局、ココカラファイン、サンドラッグなど)
- 調剤薬局(処方せんを受け付ける薬局の、一般用医薬品コーナー)
- スーパーマーケットの薬品コーナー
- 一部のコンビニエンスストア(薬の取り扱いがある店舗)
「のどが痛いな」と思ったら、とりあえず近所のお店に行けば手に入る、という安心感がオラドールSトローチにはありました。
オンラインショップでの販売
もちろん、実店舗だけでなく、大手オンラインショップでも普通に購入が可能でした。
- Amazon(アマゾン)
- 楽天市場
- Yahoo!ショッピング
- LOHACO(ロハコ)
- 各ドラッグストアのオンラインストア
風邪の季節の前にまとめ買いしたり、他の日用品と一緒に注文したりと、オンラインでの利用者も非常に多かったです。
しかし、販売中止となった現在、これらのオンラインショップでも「在庫なし」「取り扱い終了」の表示が並ぶばかりです。
【注意】フリマアプリ(メルカリなど)での現状
「どうしてもオラドールSトローチが欲しい!」という方が、次に探しに行くのが「メルカリ」や「ラクマ」などのフリマアプリです。
実際に検索してみると、販売中止を惜しんだ人が買いだめしていた「未開封品」が、少数ですが出品されていることがあります。
しかし、これには非常に大きな注意点があります。
- 価格の高騰: 当然ながら、もう手に入らない希少品として、定価の何倍もの高値で出品されています。「のどが痛いから今すぐ欲しい」という需要に応えられる価格ではありません。
- 使用期限の問題: 前述の通り、製造が終了してからすでに数年が経過しています(2025年現在)。出品されている製品の使用期限が切れている可能性が極めて高いです。医薬品の使用期限切れは絶対にNGです。
- 保管状態の問題: 医薬品は、光や湿気、温度変化に弱いデリケートなものです。個人宅でどのように保管されていたか分からず、品質が劣化している可能性があります。
- 法律上の問題: そもそも、医薬品(指定医薬部外品含む)を許可なく個人が転売する行為は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に抵触する可能性があります。
結論として、フリマアプリなどでオラドールSトローチを探して購入することは、健康面・安全面・金銭面、あらゆる観点から全くおすすめできません。
「あの味が懐かしい…」という気持ちは分かりますが、ぐっとこらえて、後述する代替品を探すのが賢明な判断です。
・「もう買えないの?」販売中止の決定打となった背景事情を深掘り
・類似品で代用できる?成分が近い代替トローチ徹底比較
・販売再開の可能性はある?メーカーへの問い合わせ状況と最新情報
・【必見】今後ののどケアに!成分・効果で選ぶおすすめトローチ3選
オラドールS愛用者が続出!高い評価を得ていた魅力と特長

販売中止になってから、改めて「オラドールSトローチがいかに優れた製品だったか」を痛感している方も多いのではないでしょうか。
なぜ、オラドールSトローチはこれほどまでに多くの人々に愛され、「これじゃないとダメ」と言わしめるほどの地位を確立したのでしょうか。
その魅力を、愛用者の声とともに振り返ってみましょう。
魅力その1:独特の風味と「効いてる感」
オラドールSトローチの最大の魅力は、やはりその「味」と「風味」でしょう。
スーッとする清涼感がありながらも、キツすぎない。
ほのかな甘みがあり、薬っぽさ(特にCPC系の苦み)が少ない。
ゆっくり舐めていると、じんわりとのどの奥に成分が染み渡っていくような、独特の「効いてる感」がありました。
SNSなどでも、
- 「あの味が好きだったのに…」
- 「他のトローチは苦くてダメだけど、オラドールだけは舐められた」
- 「ミント系が苦手な私でも大丈夫だった」
といった声が非常に多く見られます。
殺菌成分「塩化デカリニウム」と、生薬成分、そして香料などのバランスが、奇跡的とも言える絶妙な風味を生み出していたのです。
魅力その2:「殺菌」と「抗炎症」のダブル効果
「のど飴を舐めても、その場しのぎにしかならない…」
そんな経験はありませんか?
オラドールSトローチは、ただの清涼菓子ではなく、「指定医薬部外品」。
前述の通り、「塩化デカリニウム」による殺菌作用と、「カンゾウ」による抗炎症作用を併せ持っていました。
のどの痛みの原因となる「バイ菌」を退治しつつ、すでに起きてしまった「はれ」も鎮めてくれる。
このダブルのアプローチが、「舐め終わった後も、痛みが和らいでいる」という確かな実感につながっていました。
特に、「風邪のひきはじめの、あのイガイガした感じ」や、「声を使いすぎてヒリヒリする時」に、オラドールSトローチは絶大な信頼を寄せられていました。
魅力その3:口の中に長くとどまる「トローチ」という形状
のどのケアにおいて非常に重要なのが、「有効成分を、いかに長く患部(のど)にとどまらせるか」ということです。
その点で、「トローチ」という形状は非常に優れています。
(トローチは、英語の「Troche」から来ており、口の中でゆっくり溶かす薬の剤形を指します)
オラドールSトローチは、硬めの錠剤で、すぐに噛み砕けてしまう飴とは違い、口の中でゆっくりと時間をかけて溶けていきます。
その間、唾液に溶け出した有効成分が、継続的にのどの粘膜に触れ続けることになります。
これが、スプレー薬やうがい薬の一時的な効果とは違う、持続的な効果感を生み出していました。
穴あきトローチ(ドーナツ型)だったのも、口の中で転がしやすく、割れにくいという工夫があったのかもしれませんね。
魅力その4:コストパフォーマンスと入手のしやすさ
そして、忘れてはならないのが「手頃な価格」と「入手のしやすさ」です。
のどが痛い時は、一日に何度もトローチを舐めたくなります。
オラドールSトローチは、20錠入りで数百円程度と、非常にリーズナブルな価格設定でした。
(店舗によって価格は異なりますが、おおむね500円~700円前後で販売されていることが多かったようです)
1錠あたりの単価が安いため、のどの不調を感じたら「とりあえず舐めておく」という使い方が気兼ねなくできました。
そして、どこでも買える安心感。
この「いつもの定番」としての地位が、多くの愛用者を生み出した大きな理由の一つです。
「もう買えないの?」販売中止の決定打となった背景事情を深掘り

「理由その1~3」で挙げた内容は、あくまで一般的な推測です。
では、オラドールSトローチの販売中止において、特に「決定打」となった事情はなかったのでしょうか。
第一三共ヘルスケアの公式な発表を探しても、「オラドールSトローチの販売中止について」という独立したプレスリリースは見当たりません。
多くの場合、こうした一般用医薬品の製造終了は、医療関係者向けの「製造中止品一覧」のようなリストにひっそりと掲載されるか、問い合わせて初めて判明するケースがほとんどです。
しかし、業界の動向から、もう少し踏み込んだ背景を考察してみます。
競合製品の台頭と市場の変化
ここ10年ほどで、のどケア製品の市場は大きく変化しました。
- 高機能なのど飴の登場: 「龍角散のどすっきり飴」に代表されるような、生薬やハーブを配合した高機能なのど飴が爆発的にヒットしました。これらは医薬品ではありませんが、「のどに良い」というイメージで、トローチの市場を一部奪っていきました。
- スプレータイプや液体タイプの多様化: 「のどぬ~るスプレー」や「イソジンうがい薬」など、トローチ以外のケア用品も進化し、より直接的に患部を狙える製品が人気を集めました。
- 競合トローチの存在: 「ヴイックストローチ(大正製薬)」や「コルゲンコーワトローチ(興和)」など、強力なライバル製品も常に存在していました。これらの製品は、テレビCMなども積極的に行い、ブランド力を高めていました。
オラドールSトローチは、どちらかというと「知る人ぞ知る、昔からの定番品」というポジションでした。
派手な宣伝をあまり行っていなかったため、新しい顧客層を取り込むのが難しく、既存の愛用者の高齢化とともに、市場全体でのシェアが徐々に低下していた可能性があります。
「塩化デカリニウム」という成分の特殊性
先ほど、オラドールSトローチの最大の魅力は「塩化デカリニウム」にあると書きました。
しかし、これは諸刃の剣だったのかもしれません。
市場の主流な殺菌成分が「CPC(セチルピリジニウム)」である中、「塩化デカリニウム」を使い続けることは、メーカーにとって調達コストや製造ラインの維持において、非効率的だった可能性があります。
「他の製品と成分を共通化(CPCに統一)した方が、大量生産できてコストも下がる」
こうした判断が働いたとしても不思議ではありません。
私たち愛用者にとっては「唯一無二の魅力」であった成分が、メーカーにとっては「整理対象の特殊な成分」になってしまった…という、悲しいすれ違いが起きていたのかもしれませんね。
実際、オラドールSトローチの販売終了後、第一三共ヘルスケアは「ルル」ブランドや「ぺラック」ブランドののどケア製品に注力しているように見えます。
これらは、より市場のニーズが高い(と判断された)成分構成や、ブランド力のある製品群です。
結論として、オラドールSトローチの販売中止は、特定のトラブルによるものではなく、「市場の変化」と「経営戦略(選択と集中)」の中で、その長い歴史的役割を終えた、というのが真相に近いのではないでしょうか。
類似品で代用できる?成分が近い代替トローチ徹底比較

「オラドールSトローチがもう買えないのは分かった。じゃあ、代わりになる薬はないの?」
これが、今一番知りたいことですよね。
残念ながら、先ほども述べた通り、「塩化デカリニウム」を主成分とした一般用医薬品のトローチは、現在(2025年時点)の日本市場には、ほぼ存在しません。
「全く同じもの」を求めるのは、非常に難しい状況です。
しかし、オラドールSトローチが持っていた「役割」…つまり、「殺菌成分」と「抗炎症成分(生薬)」の組み合わせに近い製品は存在します。
ここで、オラドールSトローチの「代替品」となり得る類似トローチを、成分の観点から徹底的に比較・紹介します。
代替品を探す上での3つの方向性
オラドールSトローチの代替品を探すには、3つの方向性があります。
- 【方向性1】殺菌成分「CPC」+ 抗炎症成分(カンゾウなど)配合のトローチ
- 【方向性2】殺菌成分「CPC」+ 去痰成分(キキョウなど)配合のトローチ
- 【方向性3】抗炎症成分(トラネキサム酸など)を重視したトローチ
オラドールの良さが「殺菌+抗炎症+去痰」のバランスにあったことを考えると、これらの要素をいかにカバーできるかが鍵となります。
【代替品候補1】龍角散ダイレクトトローチ マンゴー
まず、オラドールSトローチが持っていた「生薬(キキョウ・カンゾウ)」の両方、または片方を含み、かつ「殺菌成分」も含むトローチを探しました。
そこで非常に近しい存在となるのが、「龍角散ダイレクトトローチ マンゴー」です。
| 製品名 | 龍角散ダイレクトトローチ マンゴー | (参考)オラドールSトローチ |
|---|---|---|
| 殺菌成分 | セチルピリジニウム塩化物水和物 (CPC) | 塩化デカリニウム |
| 抗炎症成分 | カンゾウ末 | カンゾウ抽出末 |
| 去痰成分 | キキョウ末、セネガ末 | キキョウエキス |
| 特徴 | 生薬成分が豊富。 シュガーレスでマンゴー風味。 |
バランス型。 |
ご覧の通り、殺菌成分こそ違いますが、「キキョウ」と「カンゾウ」という2大生薬を両方とも配合しています。
これは、オラドールSトローチの処方構成に非常に近いです。
味は「マンゴー風味」と、オラドールSとは異なりますが、薬っぽさが抑えられていて舐めやすいという評価が多いです。
「オラドールの生薬感が好きだった」という方には、最も試していただきたい代替品候補です。
こちらはAmazonや楽天市場でももちろん取り扱いがありますよ。
【代替品候補2】コルゲンコーワトローチ
次に、抗炎症成分として「カンゾウ」を配合し、かつ殺菌成分も含むトローチです。
それが、興和の「コルゲンコーワトローチ」です。
| 製品名 | コルゲンコーワトローチ | (参考)オラドールSトローチ |
|---|---|---|
| 殺菌成分 | セチルピリジニウム塩化物水和物 (CPC) | 塩化デカリニウム |
| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸二カリウム (カンゾウの主成分) |
カンゾウ抽出末 |
| 去痰成分 | セネガ乾燥エキス | キキョウエキス |
| 特徴 | カンゾウの主成分を配合。 清涼感が強め。 |
バランス型。 |
「グリチルリチン酸二カリウム」というのは、オラドールSにも含まれていた「カンゾウ」の主要な有効成分を抽出したものです。
つまり、「抗炎症作用」が期待できます。
キキョウは含まれていませんが、代わりに「セネガ」という別の去痰生薬が含まれています。
「殺菌+抗炎症+去痰」という3つの役割をカバーしている点で、これもオラドールSの代替として非常に優秀です。
メントール感がやや強めなので、スーッとするのが好きな方に向いているかもしれません。
【代替品候補3】ヴイックス メディケイテッド ドロップ
これは「トローチ」ではなく「ドロップ(飴)」ですが、代表的なのど薬なので比較対象に入れます。
大正製薬の「ヴイックス メディケイテッド ドロップ」です。
| 製品名 | ヴイックス メディケイテッド ドロップ | (参考)オラドールSトローチ |
|---|---|---|
| 殺菌成分 | セチルピリジニウム塩化物水和物 (CPC) | 塩化デカリニウム |
| 抗炎症成分 | (含まない) | カンゾウ抽出末 |
| 去痰成分 | (含まない) | キキョウエキス |
| 特徴 | 殺菌消毒に特化。 様々なフレーバーがある。 |
バランス型。 |
ヴイックスの主な役割は、殺菌成分「CPC」による「殺菌・消毒」です。
オラドールSトローチが持っていた「抗炎症(カンゾウ)」や「去痰(キキョウ)」の生薬成分は含まれていません。
したがって、「のどが腫れて痛い」「たんが絡む」という症状よりも、「風邪の予防で殺菌したい」「のどのイガイガをスッキリさせたい」という用途に向いています。
オラドールSの風味とは全く異なりますが、「殺菌効果」を重視するなら選択肢の一つです。
まとめ:オラドールS難民へのおすすめは?
結論として、オラドールSトローチの「殺菌+抗炎症+去痰」というバランスの取れた処方に近いのは、 「龍角散ダイレクトトローチ マンゴー」または「コルゲンコーワトローチ」の2択と言えるでしょう。
どちらもAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどで簡単に手に入ります。
まずはこの2つを試してみて、ご自身の好みや体質に合う方を見つけていただくのが、「オラドールS難民」を卒業する一番の近道だと思いますよ!
販売再開の可能性はある?メーカーへの問い合わせ状況と最新情報

「代替品もいいけど、やっぱりオラドールSトローチが復活してほしい!」
そう願う愛用者の方は、本当に多いです。
では、オラドールSトローチが「販売再開」される可能性は、果たしてあるのでしょうか?
この点について、第一三共ヘルスケアのお客様相談室などに問い合わせた方の情報をSNSなどで探してみると、得られる回答は概ね以下のような内容です。
「オラドールSトローチは製造終了となっており、現在のところ再販の予定はございません。ご愛顧いただきありがとうございました。」
非常に残念ながら、これが現実です。
2025年現在、メーカー(第一三共ヘルスケア)からの公式な販売再開のアナウンスはなく、その可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
なぜ再販は絶望的なのか?
一度「製造終了」と判断された製品が復活するのが難しいのには、理由があります。
- 製造ラインの撤去: 販売中止の理由が「製造ラインの老朽化」や「採算性の問題」だった場合、すでにオラドールSトローチ専用の製造ライン(機械)は撤去・廃棄されている可能性が高いです。それを復活させるには、莫大な初期投資が必要になります。
- 経営判断の変更: 「選択と集中」によってラインナップから外された製品を、再びラインナップに戻すには、「以前よりも格段に売れる見込みがある」というよほどの材料がない限り、経営陣の判断は覆りません。
- 成分調達の問題: もし「塩化デカリニウム」の調達が困難になっていた場合、その問題が解決しない限り、物理的に製造ができません。
これだけのハードルを越えて販売再開に至るケースは、医薬品業界では稀です。
「復刻版」や「後継品」の可能性は?
「全く同じものでなくても、似た後継品が出る可能性はないの?」という期待もありますよね。
例えば、オラドールSトローチの「塩化デカリニウム」という強みを活かしつつ、他の部分をリニューアルした新製品が出る、というパターンです。
しかし、これも可能性は高くないでしょう。
なぜなら、メーカーはすでに「塩化デカリニウム」という成分から撤退し、「CPC(セチルピリジニウム)」や「トラネキサム酸(抗炎症成分)」などを主軸とした製品(ぺラックT錠など)に開発リソースをシフトしているからです。
私たち愛用者ができることは、残念ながら「オラドールSトローチ、今までありがとう」と感謝しつつ、前項で紹介したような、今手に入る優れた代替品に目を向けることなのかもしれません。
もし、万が一、何らかの奇跡(例えば、他社が製造販売権を引き継ぐなど)が起きて復活するようなことがあれば、それは大きなニュースになるはずです。
淡い期待を持ちつつ、厚生労働省の医薬品情報や、製薬業界のニュースは、引き続きチェックしていきたいですね。
【必見】今後ののどケアに!成分・効果で選ぶおすすめトローチ3選

オラドールSトローチという素晴らしい選択肢を失った今、私たちは「自分の症状」に合わせて、のどケア製品をより賢く選ぶ必要があります。
オラドールSは「殺菌」「抗炎症」「去痰」をバランス良くカバーしてくれましたが、これからは「今、自分はどの症状が一番つらいのか?」を考えて選んでみましょう。
ここでは、「どこストア」の視点で、オラドールSの代替という観点も踏まえつつ、現在のドラッグストアで買える強力なおすすめトローチ(及び関連製品)を3つ、厳選してご紹介します。
これらはすべてAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどで簡単に購入可能です。
おすすめ1:とにかく「はれ・痛み」を鎮めたいなら「ぺラックT錠」
「のどが腫れて、唾を飲み込むのも痛い!」
こういう時、トローチを舐めるのも辛いことがありますよね。
そんな時は、「ぺラックT錠」(第一三共ヘルスケア)が最強の選択肢の一つです。
- 分類: 第3類医薬品(飲み薬)
- 主な有効成分: トラネキサム酸、カンゾウ乾燥エキス
- 特徴: のどの炎症を抑えることに特化した「飲み薬」です。「トラネキサム酸」と「カンゾウ」のダブルの抗炎症成分が、体内から直接、のどの「はれ」と「痛み」にアプローチします。
- おすすめな人: トローチでは追いつかないほどの強いのどの痛みを感じる人。
これはオラドールSの「抗炎症(カンゾウ)」の部分を、さらに強力にしたイメージです。
殺菌成分は入っていないので、殺菌トローチ(例えばヴイックスなど)と併用するのも良いでしょう。
皮肉なことに、オラドールSと同じ第一三共ヘルスケアの製品であり、こちらが現在の主力品の一つとなっています。
おすすめ2:オラドールの「生薬感」に近い「龍角散ダイレクトトローチ マンゴー」
こちらは代替品の項目でも紹介しましたが、やはり外せません。
「龍角散ダイレクトトローチ マンゴー」(株式会社龍角散)です。
- 分類: 第3類医薬品(トローチ)
- 主な有効成分: キキョウ末、カンゾウ末、セネガ末、CPC(殺菌成分)
- 特徴: オラドールSと同様に「キキョウ」と「カンゾウ」を両方配合。さらに殺菌成分CPCも配合しており、処方構成が非常に近いです。
- おすすめな人: オラドールSの「生薬による去痰・抗炎症」のバランスが好きだった人。
風味こそ違いますが、「殺菌+抗炎症+去痰」を1錠でカバーできる万能選手。
オラドールS難民の「最初の代替品」として、最も試す価値があるトローチです。
おすすめ3:殺菌力と舐めやすさの両立「明治うがい薬P(のどフレッシュ)」
「トローチを舐め続けるのが面倒」「もっと手軽に殺菌したい」
そんな方には、スプレータイプもおすすめです。
特に「明治うがい薬P(のどフレッシュ)」(Meiji Seika ファルマ)は、携帯性にも優れています。
- 分類: 第3類医薬品(スプレー)
- 主な有効成分: ポビドンヨード
- 特徴: 殺菌成分「ポビドンヨード」(イソジンの成分)を、直接のどの患部に噴射できます。トローチと違い、すぐに有効成分が届く即効性が魅力です。
- おすすめな人: のどのイガイガを感じた瞬間にケアしたい人。外出先で手軽に使いたい人。
オラドールSの「塩化デカリニウム」とは系統が違いますが、「ポビドンヨード」も非常に強力で信頼性の高い殺菌成分です。
「殺菌」という役割に特化するなら、こうしたスプレーを常備しておくのも賢いのどケアです。
(※ヨウ素アレルギーの方は使えませんのでご注意ください)
・なぜトローチの販売中止は起こるのか?医薬品の裏事情
・まとめ:オラドールSトローチの販売中止理由と今後の対策
オラドールSトローチ販売中止に関するSNSやユーザーの反応

オラドールSトローチの販売中止が明らかになるにつれ、X(旧Twitter)や個人のブログなどでは、愛用者からの悲しみの声が相次ぎました。
「オラドールS難民」という言葉が生まれるほど、その影響は大きかったのです。
ここでは、SNSなどで見られた代表的なユーザーの反応をいくつかご紹介します。
「絶望」「ショック」…販売中止を嘆く声
最も多かったのは、やはり販売中止そのものへの驚きと悲しみの声です。
- 「嘘でしょ…?オラドールSトローチ販売中止とか絶望しかない」
- 「のどが痛い時の唯一の相棒だったのに。ショックすぎる」
- 「近所のドラッグストアを全部回ったけど、どこにもない。本当に製造終了しちゃったんだ…」
- 「なんであんな良い薬がなくなるの?意味がわからない」
このように、自分の生活にとって「あって当たり前」の存在だったものが、突然失われたことへの戸惑いが色濃く表れています。
単なる「薬」という以上に、お守りのような存在だった人も多かったようです。
「これじゃないとダメ」…代替品が見つからない苦悩
次に多かったのが、代替品が見つからない、いわゆる「難民」の声です。
- 「オラドールSトローチの代替品を探してるけど、どれも味がダメ。苦い」
- 「塩化デカリニウム配合のトローチって、他になんでないの!?」
- 「龍角散もコルゲンも試したけど、やっぱりオラドールSの効き方とは違うんだよな…」
- 「あの独特の甘さとスーッと感が最高だった。似た味のトローチ、誰か知りませんか?」
特に、「塩化デカリニウム」の風味や効き目が体質に合っていた人ほど、他のCPC(セチルピリジニウム)系トローチへの乗り換えに苦労している様子がうかがえます。
「味」という感覚的な部分が、いかに重要だったかが分かりますね。
「買いだめしておけば…」後悔と在庫情報
販売中止の情報が広まると、今度は「在庫探し」と「後悔」の声が上がります。
- 「もっと買いだめしておけばよかった…残り1箱、大事に舐めよう」
- 「メルカリで高額転売されてるのを見た。足元見すぎでしょ…」
- 「〇〇(地名)の△△薬局にまだ在庫ありました!探してる人は急いで!」
しかし、先にも述べた通り、2025年現在となっては、こうした在庫情報もほぼ皆無となりました。
フリマアプリでの高額転売は、倫理的な問題もありますが、それだけ「高くても欲しい」と思う人がいた、という人気の裏返しでもあります。(もちろん、期限切れのリスクがあるので買ってはいけませんが…)
これらの声はすべて、オラドールSトローチがいかに多くの人にとって「かけがえのない逸品」であったかを証明しています。
なぜトローチの販売中止は起こるのか?医薬品の裏事情

オラドールSトローチの一件に限らず、長年愛用されてきた一般用医薬品が、ある日突然「販売中止」になることは、実は珍しいことではありません。
「どうして、消費者の声を無視して販売中止にするんだ!」と怒りたくなる気持ちも分かりますが、そこにはメーカー側の、消費者からは見えにくい「裏事情」が存在します。
事情1:厳しくなる一方の「品質管理基準(GMP)」
医薬品の製造には、「GMP(Good Manufacturing Practice)」という非常に厳格な国際基準が求められます。
これは「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」という意味で、簡単に言えば「常に安全で高品質な薬を作り続けるためのルール」です。
このGMPは、年々厳しく改定されていきます。
昔の基準で建てられた古い製造工場や機械では、新しい基準をクリアできなくなることがあるのです。
新しい基準に対応するために工場を大改修するには、何十億というお金がかかることもあります。
メーカーは、「その莫大な投資をしてまで、この薬(例:オラドールS)を作り続けるべきか?」を天秤にかけます。
もし、その薬の売上が落ちてきていたり、利益率が低い場合、「投資する価値なし」と判断され、製造終了(=販売中止)の引き金となるのです。
事情2:原材料費の高騰と「薬価」の問題
これはオラドールSトローチの理由でも触れましたが、非常に大きな問題です。
近年、世界的な情勢不安や円安の影響で、医薬品の原材料の多くが値上がりしています。
しかし、特に医療用医薬品の場合、「薬価」といって国が薬の公定価格を決めているため、メーカーが「原材料が上がったから、明日から値上げします」と自由に言うことができません。
一般用医薬品(ドラッグストアの薬)は、薬価ほどガチガチではありませんが、それでも熾烈な価格競争があるため、簡単には値上げできません。
「作れば作るほど赤字になる」
そんな状況に陥ってしまった薬は、たとえ多くの患者さんや愛用者がいたとしても、企業である以上、製造を続けることはできないのです。
事情3:後継品・ジェネリック医薬品への移行
医療用の薬(処方薬)の世界では、「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」が主流になっています。
新薬(先発医薬品)の特許が切れると、他のメーカーが同じ有効成分で安価なジェネリックを製造・販売します。
すると、新薬を作っていたメーカーは、利益が出なくなったその薬の製造を終了し、次の新しい新薬の開発にリソースを集中させます。
オラドールSトローチは一般用医薬品なので少し事情は違いますが、「より新しく、より利益が見込める製品(後継品)」にバトンタッチするために、古い製品が整理される、という流れは同じです。
第一三共ヘルスケアにとっての「次の主力選手」が、例えば「ぺラック」シリーズだった、ということなのでしょう。
私たち消費者にとっては「愛用品の販売中止」という悲しい出来事ですが、その裏には、医薬品業界の厳しい現実と、メーカーの経営戦略が隠されているのです。
まとめ:オラドールSトローチの販売中止理由と今後の対策

この記事では、多くの人に愛されながらも販売中止となってしまった「オラドールSトローチ」について、その理由から代替品まで、詳しく掘り下げてきました。
最後に、これまでの内容を簡単におさらいします。
オラドールSトローチ販売中止の真相
- 販売中止の時期: 2022年~2023年頃から市場在庫がなくなり始め、2025年現在は完全に入手不可。
- 製造販売元: 第一三共ヘルスケア株式会社。
- 中止の理由(推測):
- 採算性の問題: 競合製品との競争や原材料費高騰で、利益が出にくくなった。
- 製造上の問題: 独自の殺菌成分「塩化デカリニウム」の調達や、古い製造ラインの維持が困難になった。
- 経営戦略: 「ぺラック」シリーズなど、他の主力製品にリソースを集中させる「選択と集中」の結果。
- 再販の可能性: メーカーは「再販予定なし」と回答しており、可能性は極めて低い。
オラドールSの魅力と、私たちがとるべき今後の対策
- 魅力: 独自の殺菌成分「塩化デカリニウム」の風味と、「カンゾウ(抗炎症)」「キキョウ(去痰)」という生薬を配合した、「殺菌+抗炎症+去痰」の絶妙なバランスにあった。
- 注意点: メルカリやフリマアプリでの購入は、使用期限切れや品質劣化のリスクが非常に高いため、絶対に避けるべき。
- 今後の対策(代替品): オラドールSの処方バランスに近い、以下の製品を試してみるのがおすすめです。
▼ オラドールSの「生薬バランス」に近い代替品 ▼
1. 龍角散ダイレクトトローチ マンゴー
(キキョウ・カンゾウ・殺菌成分CPCを配合。処方構成が最も近い)
2. コルゲンコーワトローチ
(カンゾウの主成分・去痰生薬セネガ・殺菌成分CPCを配合)
▼ 「はれ・痛み」が強い時のための備え ▼
3. ぺラックT錠
(抗炎症に特化した「飲み薬」。オラドールSの抗炎症作用を強化したイメージ)
オラドールSトローチという「絶対的エース」を失ったのは本当に残念ですが、幸いにも、現在のドラッグストアには優れたのどケア薬がたくさん並んでいます。
「塩化デカリニウム」という成分に別れを告げ、これからはご自身の症状や好みに合わせて、新しい「相棒」を見つけていきましょう。
この記事が、オラドールSトローチの販売中止理由を知りたかった方、そして「オラドールS難民」となって困っていた方々の、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





![【第3類医薬品】■ポスト投函■[第一三共ヘルスケア]ぺラックT錠 18錠](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/zagzag/cabinet/item_post01/4987107626981_m_p.jpg?_ex=128x128)